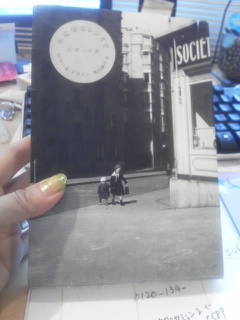ロベールドアノー展に寄せて
先週から東京都写真美術館でロベール・ドアノー展が開催されています。写真家が生まれてから100年を記念したこの展覧会には彼の60年にも渡る作品が、何と40万点ネガの中から180点厳選されて展示されました。
オープニングにドアノーの次女、フランシーヌ・デルディルさんが駆けつけてスピーチをしました。彼女とは20年以上の付き合いをさせてもらっている関係で私がにわか通訳になりました。
多くの人が熱心に耳を傾けていました、私の通訳で大丈夫だったのだろうか?
彼女のパパ、ドアノーさんに会ったのは今から24年前、1988年のことです。すでにドアノーの名前はフランスでは有名でした。
友人のカメラマン、ガストン・ベルジュレは自称ドアノーの弟子(本人は一生弟子を取りませんでした)彼からの電話で、私たち数人の友人がパリのオークションハウス、「ドルオ」に呼び出されました。
「今晩ドアノー先生の写真のオークションがある。安く落とされてしまったら大変なので、みんながサクラになって値段を吊り上げてくれ。」というのです。
我々は皆オークションの経験などなかったし、第一本当に落札してしまったらどうするの? 買えないよ。というわけでオタオタしているうちにサクサクとオークションは進み、ドアノーさんの作品の順番になってしまいました。いくらで落ちたかは覚えていませんが、我々が介入することもなく、高い値段で落ちたように思います。その時にサクラではなくてドアノーの属する写真エージェント、ラッフォ社の社員でプロフェッショナルとして来ていたフランシーヌと初めて会ったのです。
人間性溢れる彼の作品は大好きでしたので、ぜひお父上を紹介してくださいと言うと、ごく自然に「では、今度父とお宅に遊びに行きますよ」と彼女の家族とドアノーさんが我が家に夕食に来てくれたのです。余談ですが、尊敬する人が我が家で私の作った食事を食べる。そりゃ、かなり緊張します。日本と違ってそういう時にテンヤものを取ると失礼、と言うか、まっとうな主婦のするべきことではありません。下手でも家庭料理を出さなくてはいけないのです。
私は2番目の子の妊娠9か月目だったのですが、料理本を読みまくって献立を考え抜いて作ったのを覚えています。ムフタールの魚屋で生きてる貝を買ってきて、オードブルはホタテ貝の温サラダ、グレープフルーツも入れてシェリー酒のビネガーを和えて上にチャーヴィルを散らしたのを作った。と今でも覚えているほど。きっとこのメニューは死ぬまで記憶に刻まれているのでしょうね。私の頭のHDにこういうメインストリームではないディテール情報がへばりついているから頭の回転が遅くなるのでしょう。
それ以外の記憶をたどりますとドアノーさんはとても気さくでダジャレ名人でした。真面目な話が嫌いな人でした、偉そうな顔するのはもっと嫌い、自分はパリ郊外の人間、「塀の外」の人間。エスタブリッシュじゃなくて、労働者に生まれ、職人に徹しているかっこいい、たぶん江戸の職人ってこういう人たちだったのではないかと思わせるようなべらんめいな人でした。
いい仕事をするときほど知らん顔してさっとやっちゃう。苦労しているところは絶対見せない。鼻歌歌いながら、なあに、大したことありませんよ。なんて言ってしまうんですよね。実は内心、「へん!てやんでい!どうだまいったかぁ!」って腕を組んでいる感じ。日本人じゃないけれど、すごくわかった気がしてしまうのです。照れ屋で、プライドが高くて、目立つのが嫌い、いつも小さいライカを手に持って、話をしながら時々シャッターを押していました。フイルムが貴重な時代に仕事を始めたので、少ししかシャッターを押さないのです、命中率のすごく高い人でした。それもかっこいい!
話が湿っぽくなったり、シリアスになると、ヒョイと、ひょうきんになって人を笑わせないと気がすまない。そういう堅苦しいのやまじめなのは田舎っぽいっていうか(彼は江戸っ子なので)彼の美学に合わないのですね。ここいら辺私の価値観で勝手に決め付けていますが。かと言って単純な人ではなかった。彼の書いた本「不完全なレンズで」を読むとわかるのですが、人を見る目は厳しかった。
;に彼は亡くなってしまったので、6-7年しかお付き合いできませんでしたが、お互いの家に呼んだり呼ばれたりで家族ぐるみのお付き合いをしました。2番目の子供が生まれたときまっさきに来てくれて、「なんてつるつるしてるんだろうこの子は、まるで石鹸ちゃん(savonette)だね.」と言って以来ドアノーさんは息子のことを石鹸ちゃんとを呼んでいました。
ドアノーは若い時代、ジャック・プレベールを取り巻く左翼若者たちのムーブメント「10月グループ」に参加していたのですが、そのことについて、私が、共産主義と一線を隔していたのか、どうかについて質問した時に彼は大変びっくりして、「日本人の若い女性が何でそんなことを聞くのか?なんて勉強家なんだ君は。」と言われてなんだか恐縮したのもホタテ貝と同じくらい覚えています。
ドアノーさんが生前決して言わなかったことがあります、それは彼がレジスタンス運動に参加していたことです。彼はカメラに出会う前、15歳で印刷工場の職人となったのですが、その頃会得した技術を生かして、ナチス占領下のパリでユダヤ人のために偽のパスポートをせっせと作っていたのです。以前ディナーに時に戦争中は何をしていたのですか、と質問した時には「いやな時代だったよ。フイルムも手にはいらなくてね、じっとしていたよ。」と言っていたのですが、実は地下に潜っていたのです。アメリカ人がナチスを追い払ってくれた時に、フランスにはにわかレジスタンスがあふれた、と言いますが、本当のレジスタンスは黙っていたのです。一本筋が通った人間、とはこういう人のことを言うのでしょう。今回の展示で、レジスタンスの印刷工場と言うのがありますが、実はこの写真はパリが解放されたあとに再現して撮ったものだということを娘さんが教えてくれました。
「父は言ってました。『彼らこそ本物の英雄であった。どうしてもそのことを記録に残しておきたかった』と。」
パリが解放された時、写真家たちには2本のフイルムが配られました。たったの36枚分です。今歴史に残るパリ解放の写真はすべてこれらの少ないフイルムでとられたそうです。で、多くの写真家がナチスと寝た女たちがリンチに会い、髪を丸刈りにされている様子を撮りましたが、ドアノーは言いました「僕は可哀そうな女たちにカメラを向けたくなかった。」

「大きな事故の現場に居合わせたこともあった。仲間は皆、馬鹿だな、儲けるチャンスなのに。と言ったのだが僕は不幸な人にカメラを向けるのはどうにも申し訳なくてできなかったよ。」それが我らが愛するドアノーです。
甘い、と思う人もいるかもしれません。でも彼が郊外の灰色の町、ぬかるみで遊ぶ子供たちや、ひしゃげたような顔の疲れた労働者を撮る時、今の人は「なんてチャーミングなパリの子供かしら」とか、「さすが味のある顔の労働者、」と感嘆するかも知れませんが、フランシーヌが言うように、彼は、パリ市の美しい建造物に住めない城壁の外の貧しい者たちが、ひどい住宅で、ひしめいているのをカメラに収めることで無言の告発をしていたのです。そこで正義感に鼻をふくらませるかと思いきや、ウインクして彼は言ったものです。「貧困は光をよく捕らえるんだよね!」「僕は彼らを利用させてもらっているのさ。」へへへって。
ドアノーさんの最後のポートレートとなった緒方拳さんの撮影のコーディネートをしました。の正月でした。ドアノーはベルヴィルのメニルモンタン公園のあたりを歩きながらここには何があった、といちいち昔のパリの話をしてくれました。今はすっかり瀟洒な住宅街ですが、昔は貧民街でボロボロの家ばかりだったそうです。どうして貧しい人の顔に興味があるのですか?と私が聞いたら。そのときにも言ってました「貧困は写真映りがいいのさ」って。「若者や金持ちはのっぺりして光が滑るんだ」確かに彼の写真はしっかり人をとらえています。それで今でも生きている。
今、恵比寿でやっている写真美術館のドアノー展を見ると、彼の眼を通して20世紀のフランスが見えます。昔のカメラはブレずに撮るのが難しかったそうですが、展示を通して、郊外の質素な家に生まれた男のブレなかった一生が見られます。写真って撮る人の視線を表します。彼はいつも言っていたそうです。僕は自画像しか撮れない。って。彼は感情移入した時しかシャッターを押せなかったそうです。ここに写っているすべてがドアノーの顔です。時にはさびしくて、躍動したり、滑稽になったり、必死になったり。人間を大切にした人間の顔です。
サラヴァ東京では昨年の1月にピエール・バルーと堀江敏幸さんと招いてドアノーの郊外を語るイベントを開きました。いつか、彼らで今のパリの郊外をめぐる散歩をしたいね。と言っていたのが印象的でした。いつか実現するでしょうか?